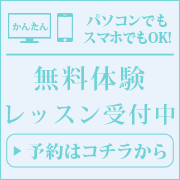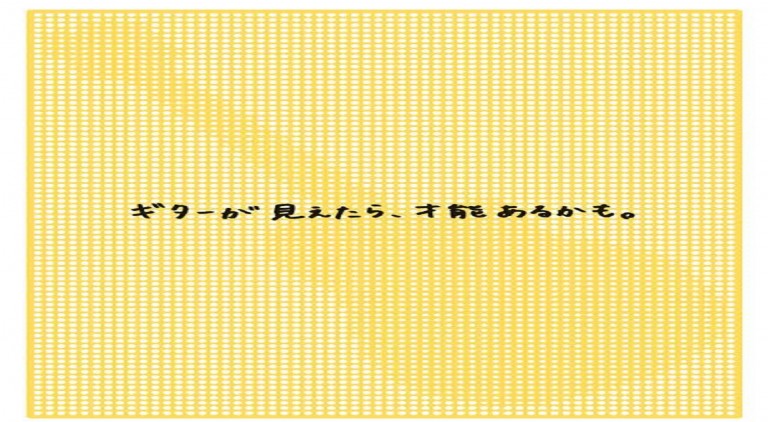DTM講師【外山 晃久】先生 プロフィール
代表の大野木です。
2018年7月よりDTM講師【外山 晃久】先生が着任しました、以下がプロフィールとなります。
よろしくお願いします。
外山 晃久(22歳)
Akihisa Toyama
DTM、エレキギター、エレキベース講師
新潟県三条市出身
中学校3年生より、ギターを始める。
高校卒業後、国際音楽エンタテイメント専門学校に入学。ギターを中心に音楽理論や作編曲などの習得に励む。
在学中、高田夜桜ミクライブやTV番組に出演する。
現在、「うつみ」名義でギタリスト・作編曲以外にも音源のMIXなどエンジニアとしても活動中。
【DTMコース】開講!
代表の大野木です!
2018年7月より【DTMコース】が開講しました!
使用DAW: Logic X
A/IF :APOGEE PROJECT Elements
Amp Simulation System : Kemper
Macコンピュータをお持ちの方、その性能をさらに使ってみませんか?
MacBookをお持ちの方が増えております。お洒落で機能も充実しておりますし、iPhone、ipadとの相性も含めてMacコンピュータをお持ちだと何かと効率が良いです。
そのお持ちのMacコンピュータでプリセットされているアプリを最大限に利用してみませんか?
楽器がなくても曲が作れる?
作曲家デビューも夢ではありません!
↓料金などの詳細はこちら
DTMコース
2018.8.7 野外ライブ【ふれあい祭り】詳細
代表の大野木です!
毎年行われている幕張本郷駅前での【ふれあい祭り】にライブ出演します!
なんと生徒さんと講師のセッションで出演します!
どんな曲でどの先生が出るのかは、当日のお楽しみです(笑)
8/7(火)、時間は17:20~です、お祭り自体はもう少し早くからやっているので、是非雰囲気を楽しんで見に来てください!
「ホテルメイプルイン」の駐車場の特設ステージが組まれます。
楽器演奏のほかにもダンス、お笑いライブなどもあるので、盛り上がっていきたいと思います。
パフォーマンスステージスケジュールはこちら
下記の動画で【ふれあい祭り】の様子が見れます。
屋台など見ると、夏祭りって感じがしますね。
是非是非、見に来てください!
ギター買った件
副代表の仲田です。
先日、ギタリストの佐々木くんと御茶ノ水で楽器屋さん巡りしました。
その時に…
不意に入ったお店で運命の出会いをしました。
Fender Mexico Classic Playerシリーズのストラトキャスターです。
こちらはメイプル指板のアルダーボディです。
50年代のストラトキャスターを模したギターですね。
Fender Custom Shopのマスタービルダー、Dennis Galuszka(デニス・ガルスカ)デザイン。
デニスのギターは2本目(笑)
ご縁があります。
しかもデニスは家具職人をやっていたという経歴。
僕がメインで使わせて貰っているMOMOSEのシニアマスタービルダー、百瀬恭夫大先生も、元々は家具職人。
家具職人にご縁があるのかもしれません(笑)
ガンガンに使っていこうと思います!